火災保険は、自然災害や日常に潜む事故などさまざまな不測の事態を補償してくれる保険ですが、時に想定していた修理費用や購入費用以上の保険金を受け取れる場合があります。
意図せず火災保険の受け取った保険金額が多く、儲けが出てしまった場合は問題ないのか。ポイントを踏まえて解説します。
・火災保険で儲けがでてもいいのか
・火災保険の特徴と注意点
・悪徳業者に注意
・より多くの保険金をもたうためのポイント
火災保険で儲けがでてもいいのか
儲けても問題ありません。
自然災害や事故などで建物や家財に損害が生じた場合、火災保険の保険金を修理費用や購入費用に充てることができます。損害を補償するための保険ですので、「修理や購入にかかった金額=保険金額」になるわけではなく、保険金額が修理費用や購入費用よりも上回ることがあります。
従って、結果として儲けてしまったということが起こり得るのです。
また、保険金は損失を埋めるためのものであり、利益ではないため、個人や個人事業主の場合は税金の対象外になります。また、法人の場合は益金として課税対象になりますが、圧縮記帳の適用により課税の延期が可能です。
火災以外の被害も対象になる
風災、水災、雷災、雪災、雹災などの自然災害、うっかりや偶発的な事故も対象
火災保険は、火災だけでなく、風災、水災、雷災、雪災、雹災などの自然災害にも適用することができます。また、火災保険は、加入されている保険が、「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財の両方」とで補償される内容が変わってきます。
保険金の使い方に制限はあるのか
使い道に制限なし
火災保険から支払われた保険金には、どのように使うかといった制限はありません。
修理方法も問われません。保険金を受け取った後に保険会社が関与することもないので、保険金を生活費や娯楽、貯金など修理以外の用途に使ってもなんら問われることはありません。
申請は何度でも可能
火災保険は契約期間中であれば何度でも申請できます。(上限金額まで支払われた場合以外)また、何度利用しても保険料は変わりません。
火災保険申請の依頼業者にしか修繕を頼むことはできないのか
自由に選ぶことができます。
修理を依頼する工事業者も、保険の契約者が自由に選ぶことができます。保険金申請のために見積りをとったからといって、その業者に工事の依頼をしなくても大丈夫です。
保険金額が確定したら、相見積をして費用を比較してみるのも手です。
火災保険申請の注意点
火災保険を使って建物の修理を行い、結果として保険金が残り儲かってしまっても問題ないのですが、故意に稼ぐことを目的とした場合、違法となるケースがありますのでご注意ください。
虚偽申請
火災保険は、自然災害や事故を補償する保険なので、経年劣化や故意による損害は補償対象外となります。
しかし、保険金を受け取るために、経年劣化であるにもかかわらず自然災害と見せかけて請求したり、自分で建物を傷つけて、あたかも自然発生的な不具合に見せかけて保険金を請求するのも、虚偽申請になります。
虚偽申請は、保険金をだまし取る行為であり、虚偽書類を作った人も申請した人も、保険金詐欺に該当します。
悪徳業者にご注意
- 火災保険を使って修繕を行う際、保険金額が確定する前に修理業者と工事契約をしてはいけません。保険金が必ず下りるとは限らないからです。
- 不要な工事までも勧めてきて、保険金を上回る支払い金額にしようと誘導してくる。
- 100%おりるというような発言をしてくる。
- 虚偽申請を申告させようとしてくる
火災保険申請とリフォームは別に考える
最も失敗する確率が減るのは、「火災保険申請」と「リフォーム」を別に考えることです。
すべてを一社に託してしまうことにより、相手にすべての選択権を握られてしまいますが、それぞれを分けて別にしておけばそれだけ失敗のリスクも減らすことができます。
まず、最初に火災保険の申請を、火災保険申請の専門サポート会社にお願いすることです。
火災保険の申請を専門としていますので、建物や火災保険両方に詳しい会社が多いのが特徴で、認定された保険金の一部を報酬として支払う必要はありますが、予算を確保してからリフォーム工事の検討をすることができるのが特徴です。
火災保険の申請方法
まずは基本的な保険申請の手順と流れを解説していきます。
- step.1 保険会社から申請書類を取り寄せる
- step.2 建物の損害状況を調査する
- step.3 申請書類を保険会社に返送する
- step.4 保険会社による審査
- step.5 認定、入金
火災保険申請の必要書類
契約者が自分で用意する書類
- 保険金請求書
基本的な情報を記載する用紙
・氏名、住所、連絡先
・申請する火災保険の証券番号
・保険金の支払い口座情報など
- 事故内容報告書
被害状況などを記載する用紙
・事故日、事故状況
・修理費用
・事故状況の図面など
※火災保険申請サポートの場合は別途作成してもらえる
業者に用意してもらう書類
- 工事の見積書
修理の内容と費用(材料、工賃、人件費など)
- 物件と被害状況の写真
対象となる物件と被害箇所の写真(災害などで損害の出ている箇所)
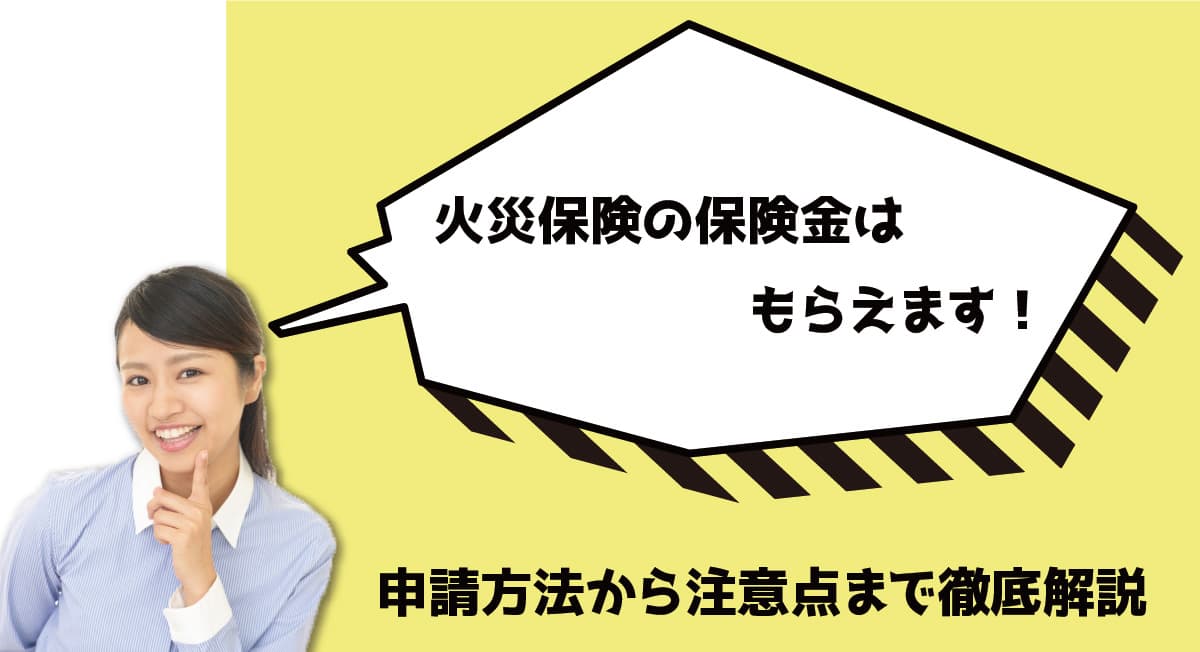
火災保険申請サポートの利用
- 火災保険申請をする時間がない
- 火災保険申請が不安
火災保険申請サポートを利用すれば、プロが書類作成や説明を手伝ってくれるため、加入者本人の時間や労力は使わなくて済む上に、プロの視点と知識のサポートを受けられ、保険金の認定率や受取金額がUPする傾向があります。
サポートを受けて保険金を受け取れた際には、金額に対して30%前後の手数料が発生します。しかも、成功報酬型のため、万が一審査に通らず保険金が受け取れない結果になってしまっても、利用者に無駄な費用が発生する心配はありません。
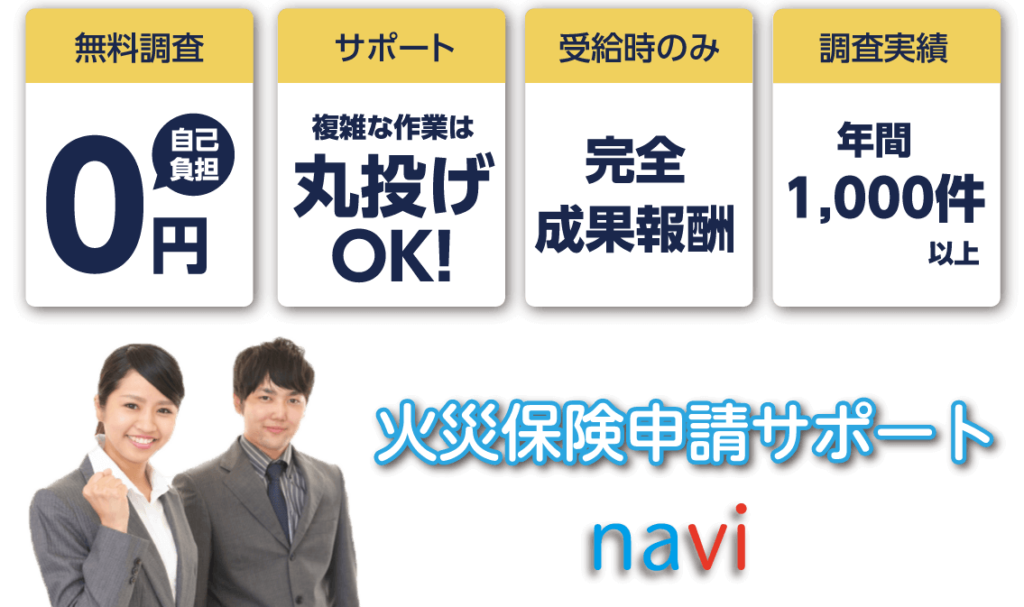











コメント